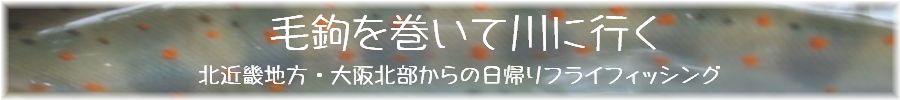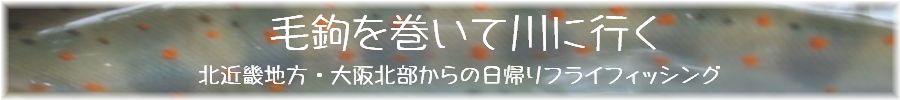そろそろ締めくくります。道具を揃えてから、何日経過されたかは人それぞれでしょうが、自作の毛鉤で釣れた日・・釣れた魚は絶対に忘れられないと察します。
何はともあれココまで到達されたならば、おそらくこれからもこの釣りを趣味として続けて行かれることであろうと察します。
私も含めて私の周りを見渡しても・・・
自作の毛鉤で魚を釣った者でフライフィッシングを止めた者はおりません。
着々と個々それぞれに楽しむ様になっております。
しかし、振り返ると・・
「自作の毛鉤で釣れた日が、この釣りの入口に立った時」
・・・である様な気がします。
タイングに傾向するもよし、キャスティングを極めるのもよし、海外ブランドの道具やバンブーに走るのも人それぞれで楽しみ方に一定の法則や基準はありません。
ニンフを好まれるのもドライ一辺倒で進まれるのも、バス等・・鱒類以外の魚に走られるのもご自分でお決めになられるのが一番です。
そしてここまで来れば、あらためてこの際これまで回避してきた「迷い」を受け入れるのも良いかもしれません。
さて、更なるステップアップを目指しこの入口の段階から進んで行かれ様とされる方々に私の拙い経験から以下に列挙させて頂きます。
但し、これらがステップアップへのアドバイスになっているのか?足を引っ張る阻害要因となって居るのかは、正直わかりません。
従って、単なる個人の意見に留めてご参考程度と考えて下さい。
<ロッド選び>
生涯一本で終わろうハズもなく、色々と物色されるでしょう。かなり大雑把に示せば同一番手では長くなる程、調子の差ぐらいしか感じ取れませんが、短くなる程、調子を含めて曲がり具合や復元スピードが気になり、拘れば難しい選択になる様な気がします。
また、購入したロッドが規定番手のラインを乗せて、柔らかすぎる/硬すぎる・・とお感じであれば、愛想を尽かして転売される前に・・
「規定番手を無視して柔らいと感じるロッドには軽めのラインを、
硬いと感じるロッドには重めのラインを乗せて試される事」
・・・をお勧め致します。一変してお気に入りのロッドとなるやもしれません。
そもそもAFTMAで規定される番手はグレインと言う重さで定量的に定められますが、これはライン先端9mに対してであり、これが適合するロッドの場合は、極端な言い方をすれば「先端9mの重量基準で定まった番手で称されるラインを投げるに適合する。」と、どなたかが定性的にお決めになった番手です。拘り過ぎても仕方がありません。
<リール選び>
巷の論評を参考にご自分の趣味で決めて下さい。私としてはあれこれ様々なリールを持たれるよりも・・
「同じリール(または替スプール)で揃えるのが、臨機応変に対応できる」
・・・様な気がします。
実際、リールは金を掛けなくてよい・・と申し上げておきながら、私自身、一部に3万円以上する海外メーカーのリールも有してます。購入理由はライフタイムギャランティと機能面です。・・と言いたい気持ちはあります。間違ってもクリック音やデザインが気に入った事だけではない・・と自分では思いたいですが客観的に冷静に判断すると、単純に物品所有の自己満足だけで釣技を支える機能面では殆ど効果を認めません。
私が行うフライフィッシングにおいて、リールとは所詮この程度のものです。
<リーダー&ティペット>
一概に示せませんが、長さがある程度定まれば、浮かせるか/沈めるかを考えた後、硬い/柔らかいを考慮されるのが良いかもしれません。
<キャスティング>
巷で頻繁に語られるダブルホール・・・実際、私も上手くできません。
私としては、まず一定のリズムでラインの乗り(前途した妖怪「ゴム紐引っ張り」)を感じるタイミングが肝と思われます。
巷の文章でよく「4拍子」の件をお見受けしますが、これは「行進する様な4拍子のリズム」ではなく、「スキップする様な4拍子のリズム」である気がします。
<ドライフライ>
色は釣り人側の都合で決めて、魚の都合でシルエットとサイズを勘案すれば悪い方向には進まないと思われます。シビアなライズハントを除けば・・・
「漁獲を求めるに、多くの種類を持つ必要はない」・・と言えます。
私が多くの種類を持つ理由は「色んな毛鉤で釣ってみたい」と言う釣り人側の事情が支配的です。
<ニンフフライ>
「ドライでサッパリなのでニンフ・・」とおっしゃる釣り人のご意見よりも、極少数派と察しますが・・「ニンフでサッパリなのでドライ・・」とおっしゃる方(・・が居られるかは存じ上げませんが・・)のご意見を参考になさるのが良いかもしれません。
つまりニンフをメインにされておられるご意見を尊重すべきです。私は前者の為、あまりアテにはなりません。
理由は簡単でドライをメインにされておられる方は釣れない時にニンフを用います。
雪シロが出たから・・
濁りがキツイから・・
水温が低いから・・と言う理由でニンフを持ち出されますが・・・
「これはニンフに適したケースではなく、ドライに適さないケース」
・・・と捉えるべきでしょう。
<渓流釣り>
釣り場となる河川渓谷や入渓する区間・時期・時間帯・天候などが支配的な事は当然ですが、その次に拘るのは「毛鉤」ではなく「アプローチ」だと思います。
ドライ・ニンフ・ウェットと様々な釣り方は時として大きく「立ち位置」が変わります。立ち位置が変わると言うことはアプローチも変わります。
「①に釣り場の条件、②にアプローチ、③④がなくて⑤に毛鉤」
・・と言う具合に考えておいて丁度で、必要以上に毛鉤に拘らないことです。
<河川管理釣り場>
釣り場の管理状況や時間帯・天候などが支配的な事は当然ですが、この場合は概ね渓流の様な「アプローチ」によって差が生じるのは極々最初のうちで・・・
「最終的には武器に匹敵する毛鉤の選定に軍配が上がる」・・のが普通です。
特にルースニングの場合はサイズやシルエットに加え、水の色(言わば濁り具合)と毛鉤の色との相関、そして何よりもその毛鉤(広い意味では仕掛け全体)が有する「沈下速度」に拘ることで喰いつきは勿論、「喰わずともジャレ付いてくるケース」が飛躍的に伸びる場合が有ります。この繊細な当りを上手くとり、間髪入れずに合わせることで釣果が爆発的に伸びるかもしれません。
<湖沼管理釣り場>
広ければ広い程、深ければ深い程、魚の付場と棚を意識することが重要だと考えます。狭い止水に近いリザーバーや人工池等は上記河川管理釣り場と同様ですが、ボートで漕ぎ出せる様な釣り場では・・
「全域で公平に釣りが成立するとは考えにくく、偏る傾向にある」
・・と言えます。
概ね、各ポイントがどの程度の水深(そもそも自分が釣ろうとするタックルで対応可能か否か)かは頭に入れておくのが無難です。
<バスフィッシング>
一年を通して、あらゆるポイントで漁獲を求めるならば・・ルアーとは比較にならない程無理が多い釣りで、足元にも及ばない気がします。概ねこの釣りを実践される方はルアーも経験済みでしょうから、釣りをなさる場所は勿論のこと・・・
「フライで釣れる条件が整った日(強いては時間帯)に竿を出すこと」
・・でしょう。おそらく想像出来ると察しますが・・・
「トップウォーターの釣りが実践できる状況が比較的容易」です。
むしろある特定の条件下で水面ではフライに軍配が上がるかもしれません。
私が想像する理由として、非常によく浮くトップウォーターのルアーでもボディーの半分以上は水面直下に沈んでおりますが、フライの場合は水面下の露出を必要最小限に留めて浮かすことが可能です。これが最大の武器の様な気がします。
それ以外は今のところ極小サイズを扱えることぐらいしかルアーに勝る点は見いだせておりません。
<ライズ・ハンティング>
当然、ライズが確認できていることが条件となりますが、一概にやり方やアプローチを限定することはできません。それぞれの状況でそれなりの判断が必要になります。
叩き上がりのドライフライフィッシングとは異なり、「毛鉤の種類」を豊富に有することが様々なケースに対応できるものとなるのは書くまでもありません。
しかしながら、この毛鉤の選定と同じぐらい「立ち位置」による格差が生じるのも事実と思われます。
「毛鉤に行き詰れば、立ち位置を変えて見られること」・・です。
同じ毛鉤でも立ち位置を変えるだけで、状況が一変することが起こりえます。
<タイング>
人それぞれの個性が出て当然と考えます。ドライやニンフを巻いている時は余り気にはしませんでしたが、ウェットを巻く様になって痛感していることは・・
「できるだけ少ない回数でマテリアルを巻き留める」練習をしておけばよかった。
・・・と言うことです。後はこれまでの経験からして・・・
「巷で名の売れた毛鉤のデザインは伊達や酔狂で決まっていない」
・・と言うことを嫌と言う程、思い知らされた感があります。
しかし、これも人それぞれでしょうから、各自で楽しまれるのが良いと思われます。
後一つ・・書かして頂くとすれば、代替マテリアルをご自分で試行錯誤される場合、色や質感はもとより、コストを優先される前に・・・
「水に対するその素材の比重を知っておくことが重要」・・でしょう。
多量に巻いて浮き沈みの問題で使い物にならない状況に陥ると、タイング自体がアホらしくなる危険性を孕みます。
まあ、色々書けばきりがなく、この辺りで終わることにします。
ココまでだらだらと書き綴った事柄は、必ずしも正解であるとは考えません。
また、用語の解説はもとより、理論や方法論は巷に任せて感覚的な部分を中心に記述して参りました為、釈然とされないかも知れません。
しかし、所詮「書き物」とはその様なものである・・とも考えます。
まずは、色々とやってみられることです。
私なんぞ・・この釣りにハマって四半世紀・・・まだまだ試行錯誤中です。
この試行錯誤が次々と湧いて出て、終わりが見えない状況です。
今後も続くであろうこのフライフィッシング試行錯誤が有意義であること・・
そして、この釣りを趣味にしようと決心された方のご健闘を・・・
心よりお祈り申し上げ、締めくくるものと致します。
ご精読頂き、ありがとうございました。
|